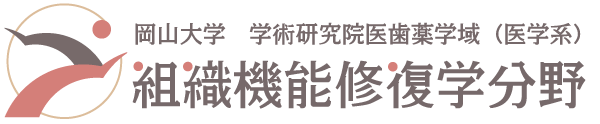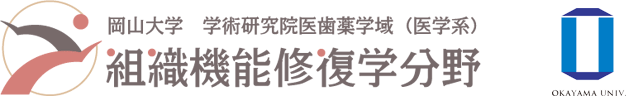Tomoyuki Ota, Tomoka Takao, Ryosuke Iwai, Takeshi Moriwaki, Yohei Kitaguchi, Yuki Fujisawa, Daisuke Yamada, Yoshihiro Kimata, Takeshi Takarada (corresponding author). Fabrication of shape-designable cartilage tissues from human induced pluripotent stem cells-derived chondroprogenitors with cell-self aggregation technique. Biomed Mater, 2023, 18(6). doi: 10.1088/1748-605X/ad02d1.
軟骨形成能を維持した状態で拡大培養できてヒトiPS細胞由来の肢芽間葉系細胞(Nature Biomedical Engineering, 2021)と、岩井先生(岡山理科大学)の開発されたCAT技術を利用して、色々な形状の軟骨組織体を作ることに成功したよ、という論文です。太田先生(岡大形成外科)が非常にがんばられました、忙しい中論文まとめて、ほんと立派です。AMED(技術開発個別課題)に採択いただき、それのご縁で木股先生(岡大形成外科)との共同研究が始まり、太田先生が臨床業務に忙しい中、立派に論文まとめていただきました。森脇先生(弘前大学)にも強度試験において大変お世話になりました、本当にありがとうございます。この論文は、うちの細胞源が、色々な形状の軟骨組織体を作ることができることを示すことができた点で、他のいろいろな再生医療研究の基点となるような仕事となります。、今後の展開に向けて課題は山ほどありますが、ひとつづつ丁寧に対応できたら、とおもいます!
耳や鼻など、形状の再現が求められる顔面軟骨再建では、三次元構造を安定して形成できる材料が不可欠です。
本研究では、ヒトiPS細胞から誘導した**軟骨前駆細胞(chondroprogenitor cells)**を出発点に、**セル自己凝集法(Cell Self-Aggregation Technique: CAT)**を用いて、スキャフォールド(足場)を一切用いずに形状を自在に設計できる軟骨組織の作製に成功しました。
この方法では、細胞自身の凝集・組織化能を利用して、リング状、チューブ状など多様な立体構造を形成できます。
得られた組織は、Ⅱ型コラーゲン(COL2)およびアグリカン(ACAN)陽性を示す成熟軟骨様組織であり、スキャフォールド材料を使用せずに力学的強度を保持できることが確認されました。さらに、培養期間や細胞密度を調整することで、数センチメートル規模の形状にも対応可能であり、複雑な湾曲や曲率を持つ軟骨構造を再現できることが示されました。
この成果は、スキャフォールド由来の免疫反応や生分解性の問題を回避しながら、**生体適合性と加工性を両立した“デザイン可能な軟骨再生技術”**の確立を意味します。