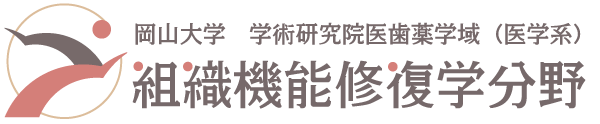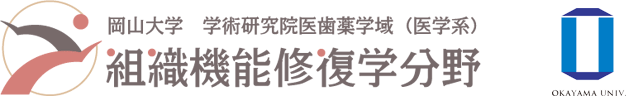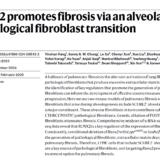遺伝子や分子の共発現パターンを解析する代表的手法「WGCNA」は、バイオインフォマティクス分野で広く用いられています。しかし、WGCNAには
①スケールフリー構造の仮定、②パラメータ調整の煩雑さ、③回帰係数を考慮しない点――という三つの限界が存在します。
宝田研究室では、これらの課題を克服する新しい解析手法 SGCRNA(Spectral Clustering-Guided Co-Expression Network Analysis) を開発しました。この手法は、スペクトラルクラスタリングと回帰解析を組み合わせることで、スケールフリー制約に依存せず、多様な生物データ(トランスクリプトーム、メタゲノム、空間トランスクリプトームなど)に適用できます。
SGCRNAは、Julia言語で構築され、オープンソースとして公開されています(GitHub: C37H41N2O6/SGCRNA)。
実際の解析では、変形性関節症(OA)トランスクリプトームデータにおいて、従来法よりも詳細なモジュール分割を実現し、小胞体ストレスや細胞外マトリックス関連遺伝子群など、疾患病態に密接に関わる遺伝子クラスターを抽出しました。
さらに、腎疾患の空間トランスクリプトームデータでは、組織内の細胞型特異的な発現モジュールを可視化し、従来法では見逃されがちな微細な転写的異質性を捉えることに成功しました。
また、**腸内細菌叢(16Sメタゲノムデータ)にも適用可能で、Faecalibacterium・Fusicatenibacter・Eubacterium属間の代謝的クロスフィーディング(共生的代謝連携)**を仮説として提示しました。
SGCRNAは、従来のネットワーク解析では前提とされていた「スケールフリー仮定」を取り払い、より現実的かつ多様なオミクスデータ構造に対応可能な次世代解析基盤としての道を開きます。